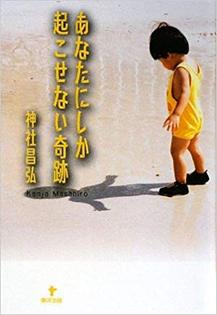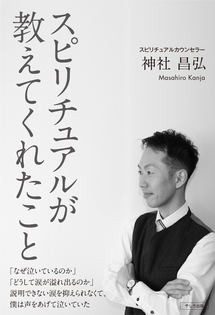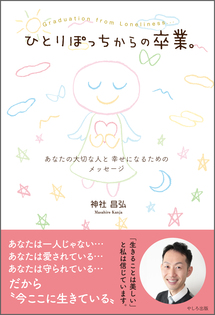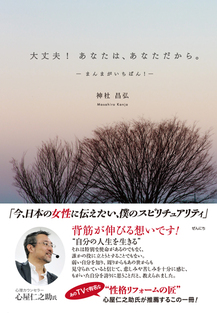- ホーム
- お布施ブログ
お布施ブログ
シャネルの香水に出会って変わった、自分の印象と香りのストーリー
2025/07/22「シャネルって、女性だけのものだと思ってた。」
たぶん、そう感じていた男性、僕だけじゃないと思います。
でも先月、香水売り場でのある出会いが、そんな思い込みをくつがえしました。
◆香水売り場で「想定外の出会い」が起きた
先月のこと。
新しい香水を探しに、新宿伊勢丹へ。
いつものようにディプティックかイソップを買うつもりでした。
でも、伊勢丹でピンとくるものがなくて、日本橋の三越へ行きました。
そして、ふと足を止めたシャネルのコーナー。
正直、それまで、シャネルは「女性用」「古風」「男には合わない」と、勝手な思い込みで避けていました。
しかし、その日は違いました。
店頭で、元気で、とっても明るいスタッフさんに声をかけられたんです。
「シャネルって、実は男性にこそ使ってほしい香りなんです。あなたにぴったりだと思います」
その一言に、なぜか胸が動いた。
そして、すすめられるままに香りを試した瞬間──
「あれ、これ、すごくいい…」
◆“香り”の向こうにある「物語」に心を打たれて
そこからスタッフさんが語ってくれた、シャネルの香水に込められた「美学」。
デザイン、素材、ロゴの配置、瓶のフォルム…。
すべてに哲学が宿っている。
──それってまるで、1冊の詩集を読むような体験。
僕は、まず「BLEU DE CHANEL(ブルー ドゥ シャネル)」を購入しました。

ガブリエル・シャネルの言葉や自伝を知っていたこともあり、実際に香りをまとうと、不思議と背筋が伸び、自分に力が宿るのを感じました。
◆そして出会った、“今の自分に必要な香り”
そのとき店員さんに勧められたのが、「香りのスペシャリスト」によるカウンセリングイベント。
7月、日本でたった1人のスペシャリストが日本橋にやってくる──
とのことで、運良く予約が取れました。
30分間、自分のライフスタイルや大切にしている価値観を丁寧に聞いてくれたあと、
「あなたには、これが必要だと思います」
と選ばれた香りが《Sycomore(シコモア)》

◆堂々たる“1本の樹”のような香り、Sycomore
「シコモア」は、秋から冬にかけての大地を思わせる、樹木の香り。
幼少期に火山に囲まれて育ったガブリエル・シャネルの記憶が、
スモーキーでビター、静かに燃えるような香りとして表現されています。
ベチバーの深み、キャラメリゼの甘い余韻…
そのすべてが、凛とした品格と、生命力を感じさせてくれます。
夏の暑さに疲れる日でも、この香りをまとうだけで、背筋がスッと伸びる。
清潔感と知性を感じさせる、まさに“纏うオーラ”のような存在。
◆シャネルを纏うという選択肢
「シャネルって、自分にはちょっと…」
そんなふうに思っていた過去の自分に、声をかけたい。
「本物は、男性・女性の枠を越えて、心を動かす」
これからも、自分の香りに責任を持って、
一滴の香水に宿る“美意識”を、
日々の中に取り入れていきたいと思います。

「なんでも言ってね」が届かない本当の理由
2025/07/18「なんでも言ってね」
「困ったら、いつでも連絡して」
そう伝えても、多くの人は、何も言わず、何も連絡してこないまま──
そんな経験、ありませんか?
僕は、カウンセラーとして20年以上、人の心と向き合ってきました。
その中で、よく耳にするのが、
「本当にしんどくなったときほど、誰にも言えないんです」
「“なんでも言って”と言われるほど、何も言えなくなるんです」
今日は、その理由と、“本当に届く言葉のかけ方”をシェアします。

❖ なぜ「なんでも言ってね」が響かないのか?
🔹遠慮がブロックになっている
「迷惑かけたくない」「わざわざ言うほどでも…」と、自分の気持ちを抑えてしまう人は多い。
🔹“何を”言っていいかがわからない
「なんでも」と言われると、逆に構えてしまい、話しづらくなります。
🔹本当に苦しいときは、連絡する気力すらない
SOSを出す力すら残っていない…ということもよくあります。
❖ 心に届く“具体的な言葉がけ”とは?
ここからが大事です。
「ドアを開けてるよ」だけではなく、「この道を通ってね」と伝えること。
🔸選択肢を示す
「迷ったら、“LINEに一言だけでも送って”って思っておいて」
🔸条件を限定してあげる
「しんどい夜とか、眠れないときだけでも連絡くださいね」
🔸連絡のタイミングを仮設定する
「来週木曜くらいに、こっちから少し様子伺わせてもいいですか?」
🔸“あなたの声が聞けると私はうれしい”を伝える
「話してくれたら、私はうれしいし、少しでもラクになってほしいと思ってます」
🔸「こんなときがサインだよ」と教える
「泣くほどじゃなくても、“ちょっと無理してるかも”と思ったら、それが合図です」
例えば、、、
無理してない?
“ちょっと聞いて〜”ってLINE一言でも送ってくれたら、それだけで私はすごくうれしいよ。
しんどくなる前に、遠慮せず、声かけてね。
人は「助けて」と言うのが下手な生き物です。
だからこそ、言葉をかける側が“助けを出しやすい環境”をつくってあげることが大事です。
「なんでも言ってね」のその先に、
「こんなときは、こうしていいんだよ」という具体的な言葉を
添えてみてください。

「神様に祈ったのに…」と思ったときに読む話
2025/07/17「神様に祈ったのに、事故に遭いました。なぜですか?」
そんなご相談を、先日クライアントさんから受けました。
神社参拝の直後だったそうです。
正直なお気持ちだと思います。
願いを込めてお参りして、真面目に生きているのに、
なぜこんな目に遭うのか──
そんなふうに思ってしまうのは、自然なことです。
でも僕は、こうお答えしました。
「神様は、罰を与える存在ではありませんよ」

確かに、辛いことがあると、
私たちは「原因」を探したくなります。
「私のせい?」
「何か悪いことをしたから?」
「もしかして、神様が怒ったのかな?」
そんなふうに思ってしまうとき、
心の中にあるのは “不安” と “期待” の両方です。
でも、こう考えてみてほしいのです。
人生って、本当に複雑にできています。
良いことと悪いことが、いつも混ざり合ってやってきます。
そして、物事の“本当の意味”は、
その場ではなく、後になってわかることのほうが多い。

たまたま神社に行った後で事故に遭ったとしても、
それが「神様のせい」なわけではありません。
むしろ、
そこで立ち止まることに意味があるのかもしれないし、
「もっと大きな災い」から守られたのかもしれない。
そう考えると、
「出来事そのもの」をどう受け取るかが、大切になってきます。
原因探しに意味はありません。
壊れたものを戻すことも、
過去に戻ることも、できません。
でも、受け止めることはできる。
「これは、何かを教えてくれている」と。
僕たちが生きているこの世界は、
“単純な善悪”では測れない複雑さを持っています。
神様だって、
私たちを裁くためにいるのではなく、
見守ってくださっている存在です。
その視点を持つだけで、
見える景色が少し変わる気がしませんか?

最後に──
もし、あなたが今、
「なぜこんなことが起きたのか」と戸惑っているなら、
まずは、「意味づけ」から自由になってみてください。
それが、次の一歩につながるはずです。
【1分で心が軽くなる】YouTubeショート動画、続々アップ中!
2025/07/11こんにちは。
カウンセラーの神社昌弘です。
今日は、僕が運営しているYouTubeチャンネル
「神社式スピリット心理学 神社昌弘のやすらぎ処方箋チャンネル」
のご紹介です。
最近、ありがたいことに視聴者さんから
「1分なのに、心がスッと軽くなる」
「短いのに深い!何度も見ています」
そんなお声をたくさんいただいています。
その理由は──
ショート動画では、お客様から寄せられたリアルなお悩みに対して、
僕と柏崎圭祐が、1分でズバッとお答えしているから。
たとえば、こんなテーマがあります。
🔸「自分が我慢すればうまくいく気がします…」
🔸「“嫌な人”の言葉に振り回されてしまう」
🔸「“いい人”をやめたいけど、やめられない」
🔸「もっと鈍感になれたらラクなのに…」
いずれも、多くの人が抱える「心のひっかかり」。
でも、誰にも相談できずに、ひとりで抱えてしまいがちなことでもありますよね。
そんな悩みに、1分でできる“視点のズラし方”や、
スピリチュアルと心理学の両方からのやさしい処方箋をお届けしています。
YouTubeショートは、サクッと見られるのが魅力。
ちょっと気分を切り替えたいときや、通勤のスキマ時間にもぴったりです。
そして何より──
「自分を責めない」
「我慢をやめる」
「心に正直になる」
そんな“本当の癒し”のヒントが、きっと見つかります。
📺 チャンネルはこちら
https://www.youtube.com/channel/UC6ong-ATFicr8n2zvmG0iRg
毎週、新しいショート動画をアップしています。
気になるテーマがあったら、ぜひチャンネル登録してチェックしてくださいね!

引き寄せが全てだと言うけれど、僕は“地に足のついた努力”も愛してる。
2025/06/28「引き寄せがすべて」
「願えば叶う」
そんな言葉があふれているこの時代。
僕も、それを完全に否定するつもりはありません。

でも――
それだけじゃ、人生は回らない。
引き寄せには「前提」があります。
それは、“本気で動いてる人のもとにやってくる”ということ。
僕はこれまで、
クローン病(指定難病)で、
8回の手術、
4年の絶食、
そして、
3万件以上のカウンセリングをしてきました。
祈ったこともあります。
願ったこともあります。
でも、それだけじゃ、救われなかったんです。
だから僕は思うんです。
✨「運」や「引き寄せ」はある。
でもそれは、“覚悟して動いてる人”に味方するものだって。

神社で願いごとをするとき、
「どうか◯◯になりますように」
とお願いするのは自然なこと。
でも、その後に何もしなければ、神様も動きようがない。
きっと神様はこう言っているんじゃないかと思うんです。
「ちゃんと動くなら、背中押すよ。
でも、何もしないまま、ただラクに叶えたいっていうのなら――
それは“甘え”だよね。」
もちろん、誰もがいつも全力でいられるわけじゃない。
時には、運に頼ってもいい。
誰かにすがってもいい。
でも、
自分の人生を“自分で迎えに行く”気持ちだけは、手放さないでほしい。
僕はこれからも、地味で不器用でも、ひとつずつ“動いていくこと”を選びます。
そして、
その動きがエネルギーになって、“引き寄せ”が自然に起こるような、そんな人生を愛したい。
願う力も、動く力も。
両方あって、はじめて人生は動き出す。
あなたにも、あなたのペースで、“動ける希望”が宿りますように🍃

-
 心が安らぐコラム
コロナ禍で、みんなが不安になっている時、カウンセラーという立場から、「いまの僕にできる社会貢献はないか?」と考
心が安らぐコラム
コロナ禍で、みんなが不安になっている時、カウンセラーという立場から、「いまの僕にできる社会貢献はないか?」と考
-
 魂が成長している人ほど、派手な奇跡を語らなくなる
スピリチュアルの世界では、ときどき「奇跡の話」が主役になります。•病気が一瞬で治った•人生が急に好転した•願っ
魂が成長している人ほど、派手な奇跡を語らなくなる
スピリチュアルの世界では、ときどき「奇跡の話」が主役になります。•病気が一瞬で治った•人生が急に好転した•願っ
-
 癒す側だった僕が、いちばん癒されていなかった頃の話
カウンセラーという仕事をしていると、よく言われます。「神社さんは、いつも落ち着いていますよね」「ブレないですよ
癒す側だった僕が、いちばん癒されていなかった頃の話
カウンセラーという仕事をしていると、よく言われます。「神社さんは、いつも落ち着いていますよね」「ブレないですよ
-
 穏便に済ませようとするほど、人は苦しくなる
「できれば穏便に済ませたい」そう思って、言いたいことを飲み込んだ経験は、誰にでもあると思います。 家族とのこと
穏便に済ませようとするほど、人は苦しくなる
「できれば穏便に済ませたい」そう思って、言いたいことを飲み込んだ経験は、誰にでもあると思います。 家族とのこと
-
 本当の占い師やヒーラーを見つける夜
スピリチュアルに酔いしれながら 昨夜、柏崎圭祐さんのラジオ番組「酔いしれナイト」に、第8回目のゲストとして出演
本当の占い師やヒーラーを見つける夜
スピリチュアルに酔いしれながら 昨夜、柏崎圭祐さんのラジオ番組「酔いしれナイト」に、第8回目のゲストとして出演