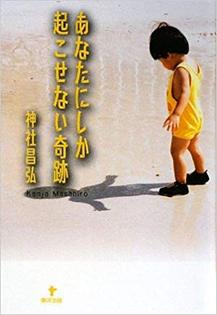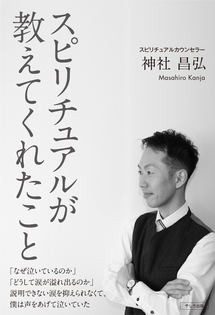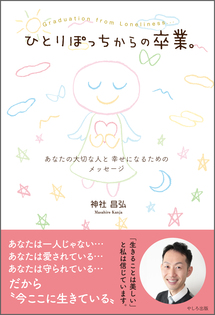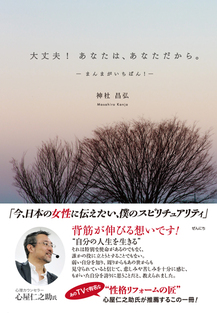- ホーム
- お布施ブログ
お布施ブログ
問題解決よりも「大切」なこと!
2020/05/12
こんにちは。
かんじゃまさひろです。
人は誰しも、苦しくなると、どうにかして悩みや不安、問題を解決したくなりますが…
実は、解決しようとすればするほど、余計に苦しくなってしまいます。
そもそも問題とは、いまここにある出来事が、自分ひとりでは「どうにもできない」状態で、行き詰っていること!
だから、自分ひとりで解決しようと思っても無理な話で、自分を追い詰める一方になります。
もし、あなたが、悩みや不安、問題を解決したいなら…
自分の在り方や考え方を一変すること!
をお薦めします。
悩みの深さは、「こうでなければいけない」「こうあってほしい」「そうじゃなきゃ困る」という自分自身の思いの深さでもあるから、「どうにもできない」事実を、ありのまま認めて、受け入れることこそ、まずは大事なんだろうなって思います。
もともと、人は、問題によって心が乱されるのではなく、日々起こりうる問題を「どう考えるか?」「どう捉えるか?」によって心が乱れるものです。
だから、解決することだけが正解だと思わずに、まずは事実をありのまま受け止入れて、問題解決だけに囚われている自分自身を解放してあげてくださいね。
誰かに頼ってもいいし…
一時保留にしてもいいし…
いますぐ解決しなくてもいいし…
ほんのちょっとゆるんで、あなた自身が解放されると、きっと、そこから優しい風が吹いてきますよ。
幸せの「四つ葉のクローバー」
2020/05/11
こんにちは。
かんじゃまさひろです。
「四つ葉のクローバーを見つけたことはありますか?」
20代の頃、僕は、どうしても見つけることができませんでした。
どんなに探しても、どこを探しても見つからなくて…
次第に、見つけられない自分が駄目な人間に思えて、カッコ悪くて、恥ずかしくて、探すことを諦めるようになりました。
駄目な自分と向き合うことが嫌で「どうせ見つからないし…」と言い訳するようにもなっていきました。
…本当は見つけたいのに…
…見つかったら、凄く嬉しくて、超ハッピーなのに…
僕は、見つけられない自分を応援できなくて、信じ切れなくて、諦めたんですね。
そうして、無難にやり過ごすことを覚え、傷つく自分を避けたり、嫌な自分を見ないような生き方になっていきました。
そんなある日、三つ葉のクローバーから、こんな風に語り掛けられた気がしました。
この時、一瞬、救われた気持ちになって、すごく感動しました。四つ葉だけが素晴らしいんじゃない!
三つ葉の素晴らしさに気づける感性も、素晴らしい!
でも…
やっぱり…
僕の心の奥底には、ずっと「四つ葉のクローバーを見つけたかった」という気持ちがあって、それを誤魔化すことはできませんでした。
いま思い返すと、自分の本当の気持ちを誤魔化していたことこそ、カッコ悪くて、恥ずかしかったんだなぁと思います。
「どうせ無理…」と諦めていたことや、言い訳をしていた自分こそが、駄目な人間だったなぁと思い知ります。
40代に突入して、ようやく、駄目な自分も、カッコ悪い自分も、恥ずかしい自分も、全部ありのまま認められるようになって、それこそが強さであり、カッコ良さであることを、少しずつ理解できるようになってきました。
だからいま、自分に正直にいること、そして自分を信じて、泥臭く自分を応援し続けることが、自分を愛することだと思っています。
そんな生き方こそが、いまの自分を一番幸せにしてくれるんだなぁと体感しています。
幸せの四つ葉のクローバーは、きっと、みんなの心の中にあるから、自分に正直に、自分を信じて、自分で自分を応援してほしいし、自分を誤魔化さないでほしいなと願っています。
何度でも何度でも「飛べる」
2020/05/10
こんにちは。
かんじゃまさひろです。
僕は、飛行機が好きです。
どれだけ好きかというと…
一日中、空港で飛行機を眺めているくらい好き。
僕のデスクには、沢山の飛行機の模型が並んでいて、もちろん、それらを眺めることも好きですが、飛行機を作ることも好きです。
時々、ミスプリントしたコピー用紙を使って「紙ヒコーキ」を作って、飛ばしています。
紙ヒコーキの良さは、手軽な面白さと、何度でも何度でも飛んでくれるところ!
自宅では、すぐに壁にぶち当たって落ちてしまいすが、形を整えて飛ばすと、やっぱりまた飛んでくれます。
もともと身軽で、柔軟性があるから、何度でも飛べるんですよね。
そんな紙ヒコーキを作って、飛ばして、見ていると…
力を抜いて、軽やかに何度でも飛ぶ楽しさを感じられます。
凝り固まった生き方が、なんだかフワっと柔らかくなる感じがします。
力を入れて、思い切り飛ばせば、すぐに痛んでしまうけれど、力を抜いて、楽しむ前提で、ゆるく飛ばせば、何度でも何度でも飛んでくれます。
旅客機だと、こんなワケにはいきませんよね?
これは、人生も一緒なんだと思います!!
力を入れ過ぎて、頑張り過ぎたら、すぐに息切れしたり、時には大事故につながるけれど…
紙ヒコーキのように、固くなく、崩れても元に戻せて、落ちることが前提で、また飛べることを信じていたら、何度でも何度でも楽しめますよね?
まるで、人生のようだと思いませんか?
今日は日曜日…
ステイホームでエンジョイホーム!
ちょっと肩の力をぬいて、ふわっと楽しんでみませんか?
僕は、お気に入りの「ハイキュー」(古舘春一氏による高校バレーボールを題材にした日本の漫画作品)を思いきり楽しみます(^^)/
飛べ!HINATA!
一番の「問題」は…
2020/05/09
こんにちは。
かんじゃまさひろです。
生きていれば、さまざまな問題が起きますよね?
自分が動くということは、日常に変化を与えるということだから、確実に「なにか」が起こってしまいます。
まわりの誰かや何かが動くということが、世界に影響を与えることだから、勝手に「なにか」が起きてしまいますよね?
だから、時には、自分には、どうしようもない問題が起きてしまいます。
そんな時に、心がけておきたいことが2つあります。
◆まず1点目は…
問題は、問題だと思った時に、問題になる!
あなたが「問題」と認識しなければ、それ以上、大きな問題には発展しません。
だから、自分ができる範囲で、できるだけのことをすればいいです。
事実、そうすることしかできませんし、もうこれ以上、問題を大きくしないでくださいね。
◆そして2点目は…
問題は、その問題のせいでうまくいかないと思い込んでいる時に、最も大きな問題になる!
つまり、問題に対する自分の「考え方の方が問題」だということです。
所詮、ひとりの人間にできることなんて限られていますから、独りでなんとかしようとしなくていいです。
あと少し視野を広めて、執着を手放して、誰かに助けてもらってください。
それでも無理なら、一時保留や棚上げにしておいてもいいですよね。
それでも、しっくりこないなら…
◆一番の「問題」は…あなたが「助けて」と言えないところにあるのかもしれません!!
真面目な人やプライドが高い人ほど、ひとりでなんとかしようとしますが、問題は、自分だけで起こっているわけではありません。
ましてや、そんなに簡単に解決することもありません。
だから…
自分にできることには最善を尽くして、それでダメなら、素直に「助けて」と頼む!
それでも無理なら…
あとは祈るしかありません。
祈りは、きっと通じますから。
良い人は「苦しい」
2020/05/08
こんにちは。
かんじゃまさひろです。
できれば「良い人」でありたい!
僕は昔から、そう思って、必死に良い人になろうとしていました。
だから…
頑張っている自分が良い人で、頑張らない人が悪い人だと勘違いしていました。
そして…
きっちりコツコツ真面目に努力する自分が良い人で、そうやらない人が悪い人だと思い込んでいました。
でも…
冷静に考えてみると、良いも悪いも自分勝手に決めていたこと。
自分勝手な基準で判断していた時点で、僕は悪い人だったのかもしれません。
そもそも…
良いも悪いもあるのが人間で、両方あるのが自然です!
良い人になろうと、頑張ったり、努力することは素晴らしいですが、もし、あなたがいま、息苦しさを感じているなら、ほどほどにして、ぼちぼちにしてください。
良い人にしがみついていると、自分も相手も苦しくなりますからね。
今日は、どうぞお気楽にお過ごしてくださいね。
-
 心が安らぐコラム
コロナ禍で、みんなが不安になっている時、カウンセラーという立場から、「いまの僕にできる社会貢献はないか?」と考
心が安らぐコラム
コロナ禍で、みんなが不安になっている時、カウンセラーという立場から、「いまの僕にできる社会貢献はないか?」と考
-
 魂が成長している人ほど、派手な奇跡を語らなくなる
スピリチュアルの世界では、ときどき「奇跡の話」が主役になります。•病気が一瞬で治った•人生が急に好転した•願っ
魂が成長している人ほど、派手な奇跡を語らなくなる
スピリチュアルの世界では、ときどき「奇跡の話」が主役になります。•病気が一瞬で治った•人生が急に好転した•願っ
-
 癒す側だった僕が、いちばん癒されていなかった頃の話
カウンセラーという仕事をしていると、よく言われます。「神社さんは、いつも落ち着いていますよね」「ブレないですよ
癒す側だった僕が、いちばん癒されていなかった頃の話
カウンセラーという仕事をしていると、よく言われます。「神社さんは、いつも落ち着いていますよね」「ブレないですよ
-
 穏便に済ませようとするほど、人は苦しくなる
「できれば穏便に済ませたい」そう思って、言いたいことを飲み込んだ経験は、誰にでもあると思います。 家族とのこと
穏便に済ませようとするほど、人は苦しくなる
「できれば穏便に済ませたい」そう思って、言いたいことを飲み込んだ経験は、誰にでもあると思います。 家族とのこと
-
 本当の占い師やヒーラーを見つける夜
スピリチュアルに酔いしれながら 昨夜、柏崎圭祐さんのラジオ番組「酔いしれナイト」に、第8回目のゲストとして出演
本当の占い師やヒーラーを見つける夜
スピリチュアルに酔いしれながら 昨夜、柏崎圭祐さんのラジオ番組「酔いしれナイト」に、第8回目のゲストとして出演